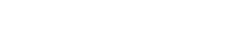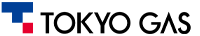
レシピの話
フランス地方料理を巡る旅


今回の舞台はノルマンディー地方! イジニー=サント=メール(Isigny Ste-Mère)のバターや生クリームと魚介のハーモニーが楽しめるレシピです。
"イシニー"というとフランスを代表する乳製品の産地。バターと生クリームはA.O.P.(原産地統制名称保護)の認証を取得していて、牛一頭あたりの放牧面積、生産地域、製法、バターの色にわたるまで細かに規定され、ブランド・品質が守られています。このバターを調べていくと魚介との相性の良さが見えてきました。というのもイズニー=サント=メールはイギリス海峡(La manche)の沿岸に位置し、元々海水が陸地に入り込んで形成された肥沃な土壌なのだそう。さらに海洋性の温暖な気候が良質な牧草を育み、育った草には海由来のミネラルやヨウ素、βカロテンが豊富に含み、その栄養素はそのまま、その草を食べて育った牛やその牛から採れるミルク、それから作られるバターや生クリームに受け継がれているのです。まさにテロワールですね。
少し歴史に触れてみると、イジニーでバターが作られ始めたのはバイキング時代(日本の平安時代に相当)。バターはバイキングにとって遠征に欠かせない貴重な栄養源でした。港町であるイジニーは中世末期にはバター取引の中心地になりました。16世紀にはその質の良さと色合いから「黄金色(またはきんぽうげ色)」のバターとして名声が高まり、パリやトゥール、オルレアンなどの上流階級の間で食されるようになりました。18世紀にはアメリカやロンドンへも輸出され、市場は世界に広まりました。有名になると今度は1930年ごろ偽物が出回るようになり、生産者が団結してブランドを守ろうと取り組み、その取り組みが今のA.O.P.へと繋がっていきました。ぜひイジニーのバターで試していただきたいところですが、日本で買うとなるとかなりの高額。ということで今回、タイミングが合わなかったこともあり、日本の発酵バターで試してみたのですが、それでもとても美味しくできました。まずはお試しいただけると嬉しいです。
♪お知らせ♪
このレシピの作り方の動画が出来上がりました。下の写真をクリックしてご覧ください。
(東京ガス業務用テストキッチン厨BO!公式インスタグラムに変遷します)


材料
<材料>(4人前)
- 帆立貝:12個
- エビ:8尾
- ムール貝:8個
- バター(イジニー産):150g
- エシャロットまたはレッドオニオン(アッシェ ※1):50g
- シードル:400ml
- 生クリーム(イジニー産):200ml
- パセリ(アッシェ):少々
- ジャガイモ(乱切り):3個
- 塩・コショウ
- リ・オ・ブール
- 米:3カップ
- バター:80g
- タマネギ(アッシェ):25g
- ニンジン(アッシェ):25g
- セロリ(アッシェ):25g
- ブイヨン:4カップ
- パセリ(アッシェ):少々
- 塩・コショウ
- フロマージュ(ラペ):適量
<フランス料理用語注釈>
※1・・・アシェ(hacher) 細かく刻む
※2・・・シュエ(suer) faire suer シュエする、細かく切った野菜を油脂の中で弱火にかけ、その水分の一部を出させて汗をかいたような状態にする
作り方
- ココット鍋でバターを熱し、アセゾネした帆立とエビをソテーし、色づいたら取り出す。
- エシャロットとじゃがいもを加え、シュエ※2するようにソテーする。
- ムール貝とシードルを加え、沸騰させて貝を開かせる。
- ムール貝を取り出し、生クリームを加え、煮詰めながら、ジャカイモに火を通す。
- 帆立、海老、ムール貝をココット鍋に戻し、味を調え、パセリを加え、お皿に盛り付ける。
- グラタン風の場合はグラタン皿に盛り、フロマージュのラペを振り、サラマンダー(天火式焼物器)で加熱する。
- リ・オ・ブールは「Quenelles de brochet à la lyonnaise/カワカマスのクネル リヨン風」のページをご参照ください。
シェフエピソード

今回はノルマンディー地方です。前回の南仏から北へ大きく移動します。これでノルマンディー料理は3品目ですね。過去2品は「Quenelles de brochet à la lyonnaise/カワカマスのクネル リヨン風」と「Poulet Vallée d'Auge/若鶏のオージュ谷風」でした。だいぶ間も空きましたので、この機会に是非バックナンバーを読み返してみてください。新たな発見があるかもしれません・・・。
さて、ノルマンディー地方ですが皆さんご存知の通り北部が海に面しているため、新鮮な魚介類や牡蠣、ムール貝などの海産物が豊富に水揚げされています。それとフランス有数の乳製品生産地でもあるので、カマンベール、リヴァロ、ポン・レヴェックなどの伝統的なフロマージュも有名です。バターや生クリームについてはカルヴァドス県とマンシュ県にまたがる地域「Isigny Ste-Mère/イジニー=サント=メール」が高品質で知られていて、クリーミーでコクのある風味が特徴の発酵バターが生産されておりフランス国内外で高く評価されています。「Isigny-Sainte-Mère(イジニー・サント・メール)」というA.O.P.(原産地名称保護)認証を受けているので、独自の製法と風味が保証されています。このイジニーはノルマンディーの乳製品の中でも特に伝統と品質を誇るメジャーブランドで、数多くの美食家やシェフ達にも広く愛用されています。ちなみに日本でもとても有名な「エシレバター」はヌーヴェル=アキテーヌ地方のドゥー=セーブル県にあるエシレ村(Échiré)で作られる伝統的な発酵バターです。こちらもA.O.P.認証を受けています。1990年代後半から2000年代初頭にかけて日本で急速に広まったのですが、私はフランスに行くまでエシレバターの存在をまったく知りませんでした。単なる無知だったのかもしれませんが・・・。
そこで今回は前出のイジニーのバターと生クリームで作る魚介料理をご紹介します。料理名は「Coquilles Saint Jacques à la crème d'Isigny /帆立貝のイジニー産クリーム煮込み」です。ノルマンディー地方を代表する料理の一つで、イジニー産生クリームとバターを使い豊かなコクと滑らかな味わいが特徴の料理です。写真では煮込んでそのまま盛り付けるアシェットとクリーミーなグラタン風に仕上げる盛り付けの両方にトライしてみました。
なのですが・・・、残念なことに、撮影までにイジニーのバターと生クリームを入手することができなかったので、今回は国産の発酵バターと生クリームで調理しました。調理行程はいたってシンプルで、煮込みとはいえ帆立貝や他材料に火を入れすぎないように調理するのがポイントです。撮影ではローヌ地方にいたときのココット調理を思い出しながら作りましたが小人数分であれば、フライパン一つでもOKです。是非作ってみてください。
▲グラタン風

研修時代の話~最後のバカンス~
ここから前回のお話の続きを。フランスでの3年間の仕事を終え、予想外に貯まってしまったフラン(在仏時)を懐に、当時も三ツ星に輝いていたモナコの「Le Louis XV-Alain Ducasse/ル・ルイ・キャーンズ-アラン・デュカス 」で食事をしてからスペインを回って、日本に帰ろうという贅沢な計画を立て、春夏のセゾン(季節)を過ごした田舎町Tain-l'Hermitage/タン・エルミタージュを出発しました。
2ème classe (2等車)の列車を乗り継ぎながら、まったく急がないゆっくりな旅です。途中、履きつぶしたサボ(厨房用靴)の買い替えに行ったり、休日にぶらぶら散歩に行っていた街「ヴァランス(Valence)」で乗り換え、次に一度だけ観光しに行った、14世紀に世界最大級のゴシック様式の宮殿の中にローマ法王庁が置かれ、中世の城壁に囲まれた旧市街も美しい「アヴィニョン(Avignon)」を通過していきます。そしてここから先は私にとって未知の世界なので景色をしっかり目に焼き付けようと車窓にもたれて外を眺めていました。が、いつの間にか眠りに落ちて、すやすやと・・・。気が付くと、とっくにお昼も過ぎていて、程なく大きな港町「マルセイユ(Marseille)」に到着。乗り換えしたかの記憶がないのですが、そのあと通った「カンヌ(Cannes)」の海岸で青白ストライプのパラソルが優雅に咲いている景色や岩場の様子や青い海の色は、今もしっかり憶えています。子供のころ、夏に江ノ島や片瀬海岸や茅ヶ崎で海水浴をして育った私にとっては夢のような、そして映画のような光景でした。色々な思い出があるリュック・ベッソンの映画「グラン・ブルー」を観て想像していた以上の景色でした。世界中のお金持ちがバカンスで集まるところだと知ってはいましたが、車窓からの眺めだけで圧倒されてしまいました。「すっげー!素っ敵ー!」「海の家は・・・やはりないな!」
小一時間列車に揺られ、心を躍らせてニース駅で下車です。予定ではニースで1日過ごしてからカンヌに向かうことにしていました。降り立ったニース駅はイメージしていたセレブな雰囲気は皆無で、そこかしこに大勢のバックパッカー達が駅の外で座りながらペットボトルの水を飲んでいる、まるで日本の地元の夜のコンビニ前を見ているような感じ。「あれ?ニース?」一瞬たじろぎましたが、宿を探しながら街をうろうろしていると、結構危険な雰囲気のところもありながらも何だか楽しそうな街だなというのが初日の印象でした。翌日からの続きのお話は「Aziminu/アジミヌ コルシカ風ブイヤベース」のぺージに書いてありますので、是非読んでみてください。結果、とっても楽しいニースで1週間を過ごしてしまい、軍資金も底をつきモナコには行けず、失意のうちに(熱い熱いニースの思い出を胸に)情熱の国スペインへと向かいました。(シェフM.T)

▶厨BO!YOKOHAMAではFFCCと共に様々なセミナーを開催しています。こちらもご覧ください。
▶ スチコンレシピ集で毎月新レシピをご紹介中。